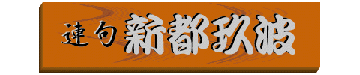
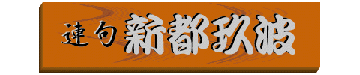
| 新都玖波連句の形式 | 既巻 | 玉助の新釈芭蕉連句 |
芭蕉翁苦吟之圖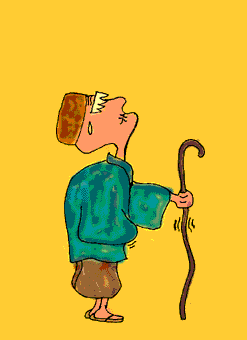 |
連句は、簡単に言えば俳句を連ねたもの。五七五(長句)の次は七七(短句)、次は長句と連ねていく形式です。2句合わさると短歌と同じ三十一文字になります。 連句には、長い歴史のなかで形成された様々な約束事があります。新都玖波連句の形式にその例を挙げて解説してあります。こうした約束事は、全体の構成を整える上で自由なあまりの野放図を避け、なにがしかの規律により、緊張にみちた自由を喜んだものとおもわれます。 連句も、やはり時代を経ると、枝葉末節、規則一点張りの煩わしい世界に陥ることがあったのでしょう。そのへんを心得て、芭蕉先生などは、かなり勝手きままにやっている節があります。この「新都玖波」では、形式は形式、でも・・・、ぐらいに思っています。 連句の肝心なところは、前の人、後の人のことを思いやりながら創ることです。心遣いの集まりといえましょう。 |
| ここでは、拙いものですが、我々で作った連句集を披露しています。興味をもたれたら皆さんもはじめてみてはいかがでしょうか。 |
|
| 動画で見る | 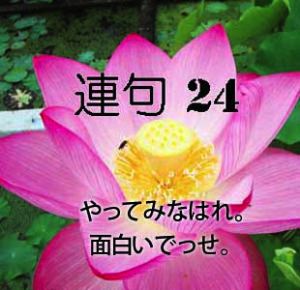 連句24 動画 連句24 動画動画で表現する新しい試みに挑戦しました。動画で広がる連句の世界をご堪能下さい。芭蕉翁も予想できなかった事態でしょう。たぶん本邦初かも知れない。(06.11.24)*Video Podcasting は都合により停止しました。You Tubeでの公開に切り替えました。 |
| リンク 同好の士 | ●猫蓑会 「芭蕉の確立した蕉風の俳諧を現代に流布させることを目的」とした一本筋の通った連句会 ●平野連歌 大阪市平野区の杭全(クマタ)神社の連歌所で催される百韻連歌 参考になります。 ●キョン太の連句道場----投句、連句講義室、作品集、リンク集等もあります。 ●歌仙張行----リンク集 ●レンキスト----(レンキストとは連句人のこととか) 東京文献センターの中に置かれた連句アラカルト 書籍の紹介も |
| 自費出版考 | ある程度句作りが溜まってくると、まとめてみたいと思うのは人情ですが、こと出版となるとなかなか敷居が高い。悪徳業者につけ込まれることもあるようです。 世の中進んでくると様々なやり方が出て来るもので、ネットを利用して在庫を持たないオンデマンド方式の出版も現れて来た。編集作業は自分持ちで、初期投資がいらないのが利点だが、業務をいつまでやっているかは不透明。見極めを付ければ一考の余地有りかも知れないが。 参考オンデマンド出版---ホンニナル出版 |
|
|
|
| お気づきのことやご意見、ご質問などございましたら、どうぞこちらへお便り願います。 執筆 涛青 |
|